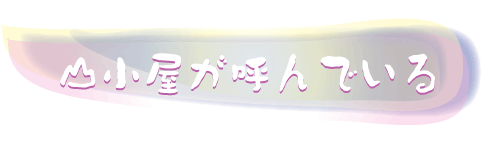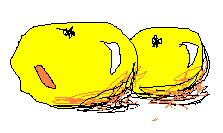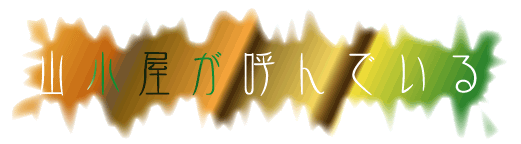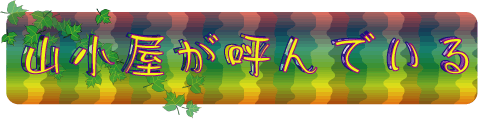坂井さん率いる高見石へのハイキングが八月五日に行われた。私も誘われていたので、行く積もりであったが、十日ほど前に、自宅で机に躓いて足の小指を痛めて参加できなかった。
当日は朝から快晴であったが、山の天気は不安定で、午後になって雨に降られたそうである。その夜、ハイキング仲間が堀越さんちでバーベキューをやることになっていた。家内は、初めての人ばかりなのは苦手だと言うので、誘いに来てくれた下の山荘のSさんの奥さんと出掛けた。
このパーティーは、自分の食べるものは自分で持っていくことになっている。冷えた缶ビール四本と腸を取った新鮮な鰺二匹、タマネギの輪切りを一個分持って出掛けた。6時半を少し回ったところであった。堀越さんの奥さんが、いつもの笑顔で迎えてくれた。「今日は別な奥さん?」と、お淑やかな奥さんが、いつになく冗談を言った。人が沢山集まっているので、今日は少し興奮気味なのであろう。
 既に10人以上集まって、池田さん夫妻を中心に甲斐甲斐しく焼き始めていた。 堀越さんちのベランダは、ベランダと言うより、建物の一部であり、可成り広い。真ん中に一本の丸太から切り出された幅広の長大なテーブルがあり、両側にこれまた長いベンチがあって、20人ぐらいは座れる。その周りにも、丸太を輪切りにしたスツールが沢山あり、3、40人は軽く収容できる。立派な屋根があるので、雨が降っても大丈夫である。
既に10人以上集まって、池田さん夫妻を中心に甲斐甲斐しく焼き始めていた。 堀越さんちのベランダは、ベランダと言うより、建物の一部であり、可成り広い。真ん中に一本の丸太から切り出された幅広の長大なテーブルがあり、両側にこれまた長いベンチがあって、20人ぐらいは座れる。その周りにも、丸太を輪切りにしたスツールが沢山あり、3、40人は軽く収容できる。立派な屋根があるので、雨が降っても大丈夫である。
食材も焼け始め、三々五々集まった人も二十人を越えたので、坂井さんが開会の挨拶を始めた。みんなの簡単な自己紹介があり、食べ始めた。
集まった人の三分の二は、私も既に知っている人達である。フランス人のポール・パンソナさん夫妻は、「殆ど此処に住み着いているんです」と挨拶した。ポールさんの奥さんは日本人で、以前から何度もお会いしたり、訪れたりしている間柄である。池田さんは「殆どこの地に居ますので、何か手伝うことがあったら言って下さい。何時でも行きますよ」と自己紹介した。私は、「年に三十数回も来て、土木工事をするのが最大の趣味です。その他山に登ったり、スキーをしたりします」等と紹介した。
ポールさんは、良く自分で料理をする。今日も、茄子やキュウリなどの野菜を煮た”ラタトーユ”を大きな鍋ごと持ってきて、「今作ったばかりです」と、みんなにご馳走した。これは私の家内もよく作る料理である。「さっぱりして、美味しい」と大評判で、最初に空になってしまった。
私が初めて合った人は、名前は忘れたが、池田さんの隣の山荘のご夫妻と、里の黒沢酒造の親戚の方で、直ぐ下の山荘に来る美しい婦人であった。また、八千穂通信という別荘のリーフレットを発行している建築家の松田さん一家が三人の子供さんを連れてやってきていた。松田さんとは、初めて話をしたが、別荘ライフについて二冊の本を書いている人で、本の中に本人の写真が出ていたので直ぐに分かった。「松田さんですね、あなたの書いた二冊の本を買って愛読していますよ」と言って挨拶した。
また、堀越さんから、「黒沢さんは、里の名家の黒沢酒造の親戚の方で、お父さんが木工好きで、80歳になった今でも、精密な工作をやっているのですよ」と紹介があった。私は、それを聞いて、意を強くした。「80歳まで出来るなら、私の土木工事や木工も、後十五年は楽しめますね」と言って笑った。
池田さんの隣の山荘のご主人は、「今日のハイキングでずぶ濡れになり、換えを持ってきていないので、こんな格好で来ました」と、ショートパンツ姿で挨拶した。夏の別荘地では、これぞ正装である。彼と堀越さんの義兄と私との三人は同じ歳であった。
パンソナさんは、お国柄で、美味しいワインを持ってきてくれた。又、堀越さんのお兄さんは、珍しい地ビールを、池田さんの隣のご夫妻は、美味しい地酒を持ってきて飲ませてくれた。みんな、人の持ってきたものを珍しがって食べたり飲んだりした。
予定の九時を大分回ったところで、坂井さんから次回十月の山行予定が発表され、お開きとなった。山にはこんな楽しい行事が時々ある。
![]()