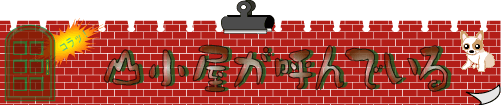
|
|
| ★猟犬に襲われる (1999.3) |
|
|
ある寒い冬の朝、一人で別荘地内を散歩していた。一本の道のドン詰まりを折り返し、緩やかな坂道を下って来た時のことである。突然道の右下の別荘から、私の体に近い大きさの猟犬、ポインターが、道に上がってくるなり私に向かって吠え掛かってきた。一瞬、「はっ」と、身の毛がよだった。毛並みから見て明らかに飼い犬である。
キルティングの防寒服を着てフードを被り、裏側に毛のある厚い手袋をして、ややごついチロリアンシューズを履いていたので、犬は不審に思ったのか、挑戦的な面構えをして近づいてきた。
回りに人気はない。五メートルまで近づいてきて、今にも襲いかかる構えで吠えたてる。武器は、全く持っていない。私は咄嗟に、素手で戦う覚悟を決めた。

正面小学校の柔道の時間に習った自然本体に構えた。戦う姿勢を示すため、一歩前に出た。犬の目を睨み据え、攻撃を待った。犬は猟犬であるから必ず飛びかかってくる。その間にも犬は怯まず腰を屈めてじわじわ近づいてくる。三メートルまで近づいてきた。飛びかかってきたらビブラムソールのチロリアンで顎を一撃しようと身構え、右足に全神経を集中した。
その時、ふと、靴紐をそれほどきつく締めていない事に気が付いた。瞬間、もしかしたら最初の一撃目で靴が脱げるかも知れないと言う思いが横切った。絶対外せない。どっちが最初に致命的な一撃を加えるかが勝負である。もし、しくじったら、どんな形になっても喉を押さえ、目玉を潰してやるぞと心に決めた。
その間二秒も有ったろうか、低い体勢で体をぶるぶる振るわせながら、じわじわ二メートルに近づいてきた。飛びかかってこようとする瞬間、口笛が聞こえた。飼い主が只ならぬ犬の吠え方に何かあったのかと確認しに来て、人に向かっているのを見たのか、呼び戻したのである。犬は戦意を解き、きびすを返して戻って行った。飼い主は卑怯にも出てこなかった。その瞬間、飼い主に対する言い様のない憎悪感が体を駆け抜けた。
飼い主は、ほっかむりを決め込み、最後まで現れなかった。「このやろう」と言う思いは今でも消えていない。しかしその時、何故かその家に怒鳴り込まなかった。
実際に犬と格闘したらどうなっていたか分からない。
大声を出していたら事態はもう少し変わっていたかも知れないが、その時は向かい合うことに全神経を集中していた。
その後何年も経つが、未だにその家の人間に合うチャンスはない。しかし、そこを通る時は何時でも小型の鉈を持って歩いた。残念ながら似たような二軒の家のどっちだったか思い出せない。それだけ興奮していたのだろう。
帰って何日か後、管理人にこの事を話した。管理人は何の感動もない素振りで私の話を聞いていた。地方自治体の管理人は深入りしたくないのだろう。しかし、そんな顔はしていたが、何処の家か知っているらしかった。
これは、もう何年も前の話である。「護身用のナイフを買わなければならないな」と思いながら未だに買っていない。
